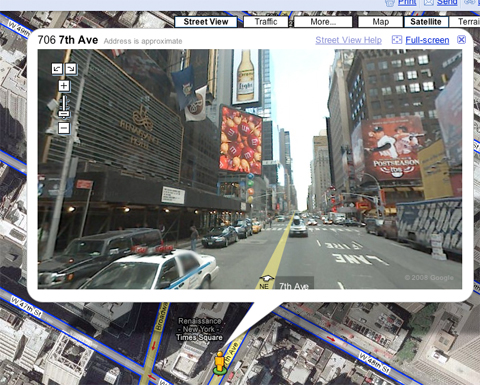「そういうつもりじゃなかったんだけど」とその子は言った。
「書き始めたら、それがずいぶん、っていうかかなり気になってるみたいだってことがわかったんだ」
「それが何だったの?」と私は聞いた。
「集中豪雨」
この子、これで関根勤のファンだというのだから、この先どうやって話を紡いでいったらいいのか、私にはとてもわからない。
「ふうん」
「集中豪雨っていうのはさ、最近まではこんなにたくさんなかったんだよ、知ってた?」
「……」
「昔は台風みたいな感じに来てたものらしいんですよ」
「悪いんですけど」と私は言った。「11時から用があるので、またにしてもらえません?」
そのあと、オフィスへ向かう電車の中で、それはごく瞬間的な短い夢だったのだけれど、私はインド洋の小さな島々で絶滅したドードーの夢を見た。20キログラム以上もあるという巨体に、申し訳程度の羽根のついた鳥だ。ドードーはいったいどんな声をしていたんだろう? そこで声の部分は聞こえないのだが、なかなか説得力のある話しぶりで、熱心に語りかけてくる。
「ドードー」と私は言いたかった。「いくらなんでもそれは手遅れだわ」
しかし私はそんなことは言わなかった、もちろん。夢がじゅうぶん短かったおかげで。